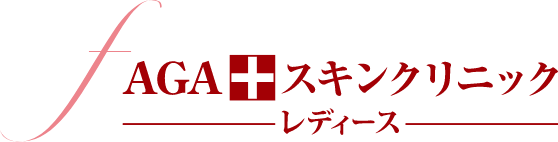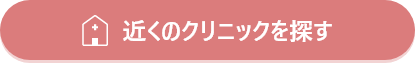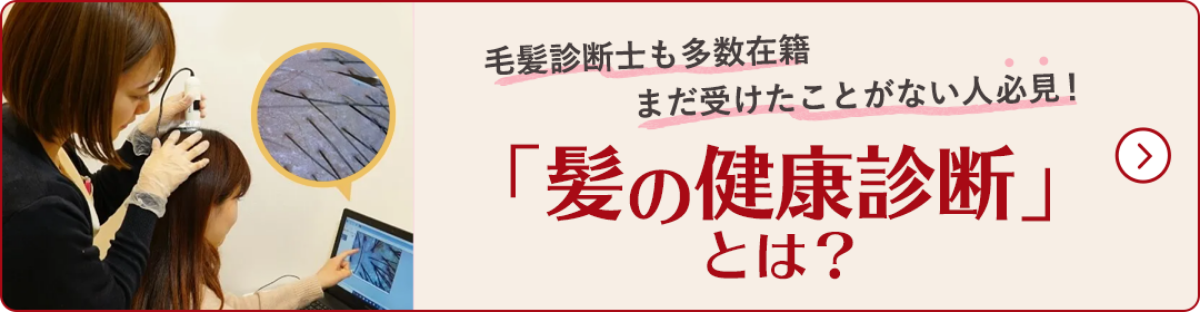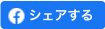お得情報・美髪ケア方法を配信中
薄毛の予防法【医師監修】女性の薄毛対策。症状別の予防・対策法
2023/09/21 更新
監修医師
AGAスキンクリニックレディース
診療顧問 田中洋平医師

【経歴】
2000年 3月 信州大学医学部医学科卒業
2007年 4月 クリニカ タナカ 形成外科・アンティエイジングセンター 開設
2019年11月 AGAスキンクリニックレディース 診療顧問 就任
女性の薄毛対策

薄毛は男性の悩みというイメージが強いことから、薄毛かもしれないと感じると、ショックを受ける女性も多いことと思います。薄毛に悩まされるとは思いもよらず、どんな対策をすればいいのか見当もつかない方もいるのではないでしょうか。
この記事では薄毛の原因やおすすめの対策、薄毛に関する噂などについて紹介します。焦らず地道にケアを続けることで、薄毛は改善する可能性があります。できることからケアを始めてみてください。
そもそも薄毛の原因とは?
薄毛の原因として考えられることを、大きく6つに分けて説明します。思い当たる原因がないか確かめてみてください。
原因1.生活習慣の乱れ
食生活の乱れや睡眠不足、運動不足、過度な飲酒や喫煙など、生活習慣の乱れは薄毛を引き起こす原因となります。不健康な生活習慣は血行不良や栄養不足、ホルモンバランスの乱れなどを招き、薄毛が進行しやすくなります。偏った食事や夜更かしが続くなど、生活習慣が乱れていないかをひとつずつ見直しましょう。
原因2. 女性ホルモンの減少
女性ホルモンは髪の毛の量に深く関わっているため、女性ホルモンが大きく減少すると、抜け毛や薄毛になりやすくなります。女性ホルモンが減少するケースとして多いのは加齢と出産です。
加齢による女性ホルモンの減少は、40代後半ぐらいから始まる場合が多いようです。体内の男性ホルモンの割合が相対的に上昇することで、ホルモンバランスが崩れ、薄毛を引き起こします。
出産も女性ホルモンの急激な減少のきっかけとなります。妊娠中は体内の女性ホルモンが通常の状態より増加していますが、出産とともに通常の値に戻るため一時的に女性ホルモンが大きく減少し、抜け毛の多い時期が続くことがあります。産後の抜け毛は、1年ほどで元に戻ることが多いといわれています。
原因3. 内臓疾患などの病気
薄毛は頭皮や髪の毛だけではなく、内臓疾患などの病気にもかかわりがあります。薄毛を引き起こしやすい病気として自己免疫疾患や甲状腺疾患などが挙げられます。
自己免疫疾患は、体外から侵入した細菌やウイルスなどを攻撃してくれる免疫が、自分の細胞を敵と勘違いして攻撃する状態を指します。毛根の細胞が攻撃されると髪の毛が抜けてしまうのです。
甲状腺疾患は、新陳代謝や髪などの成長に関わる甲状腺ホルモンの分泌が低下します。抜け毛だけでなく倦怠感や寒気、身体のむくみ、無気力などの体調不良がある場合は内臓疾患の可能性も疑い、早めに医療機関を受診するのがおすすめです。
原因4.ストレス
現代社会にはどうしてもつきまとうストレスですが、薄毛を引き起こす原因となるため注意が必要です。ストレスを発散できずに溜め込むと、自律神経の乱れを招き、血管が収縮することで血行不良に陥りやすくなります。そのため髪の毛や頭皮に必要な栄養が行き渡りにくくなるのです。
ほかにもストレスが原因で睡眠不足になったり、無意識に自分で髪を引き抜いてしまうトリコチロマニアという症状が起きたりと、ストレスと薄毛には深い関係があります。
原因5.ヘアスタイルなどによる髪への負担
気に入っているヘアスタイルがあって、毎日そのスタイルで過ごしているという方もいるのではないでしょうか。しかしずっと同じヘアスタイルで過ごすことが、髪や頭皮のダメージになってしまう場合があります。いつも同じ部分できつく結んでいたり、同じ分け目ばかりにしたりすると、その部分の髪の毛や頭皮の負担が蓄積して抜け毛を引き起こしやすくなります。
またパーマやカラーリングもダメージのもととなるため、頻繁な施術はおすすめできません。薄毛かもしれないと感じたら、パーマやカラーリングは少しお休みして、カットやアレンジでヘアスタイルのおしゃれを楽しんでみるのはいかがでしょうか。
原因6.ヘアケアの誤り
ヘアケアは毎日積み重ねるからこそ、誤っていると髪の毛や頭皮へのダメージが蓄積しやすくなります。良かれと思ってしているヘアケアで薄毛を悪化させないよう、方法が誤っていないかを確かめておきましょう。
やってしまいがちなヘアケアのミスとして下記のようなものがあります。勘違いしてヘアケアをしていないか確かめてみてください。
・清潔に保つために一日に何度もシャンプーをする。
→洗いすぎると頭皮が乾燥し、頭皮環境が悪化する原因となります。
・洗浄力がとにかく強いシャンプーを選んでいる。
→洗浄力が強すぎると必要な皮脂まで洗い流してしまう可能性があるため、優しく洗える洗浄成分のものがおすすめです。
・頭皮は気にせず髪の毛をメインに洗う。
→頭皮は髪の毛が生えるための土台であるため、頭皮をマッサージするようにしっかり洗うことが大切です。
・汚れをしっかり落とすために爪を立ててゴシゴシ洗う。
→爪を立てると頭皮に傷をつけてしまう恐れがあります。
・熱のダメージが気になるのでドライヤーは使用しない。
→髪は濡れているとダメージを受けやすく、また生乾きの頭皮は細菌が繁殖しやすい状態になります。
薄毛対策っていつから始めたらいいの?

薄毛対策は「薄くなってきたかも?」と感じたらすぐに始めるのがおすすめです。
中には、「薄くなってきた気がするけど、まだ若いし薄毛対策は大げさかな」と思う方もいるかもしれません。しかし、薄毛は放っておくと進行し症状が悪化することが多く、治療を始めても改善が難しくなることが考えられます。薄毛が気になったらできることから少しずつ対策を始めましょう。
今日から始められる薄毛対策
今日からできる薄毛対策を大きく7つに分けて紹介します。全部を一気にやろうとすると負担が大きく、挫折する可能性があるので無理なく少しずつ生活に取り入れていきましょう。
対策1.生活習慣を見直す
まずは毎日の生活習慣を見直すことから始めましょう。食生活、睡眠、飲酒や喫煙の3項目に分けて解説します。
食生活
- 食生活の見直しは「食習慣」「食事内容」の二面から見直しましょう。
食習慣は、食事の量や回数が少なすぎないかを見直すことが大切です。過度なダイエットをしていると、食事を一日一回にしたり、サラダやフルーツだけを食べたりと栄養不足に陥りやすい食習慣になりやすいため注意してください。
食事内容は栄養バランスの良いメニューにできているか、髪の毛の成長に大切な栄養素をとれているかを見直してみましょう。髪に良い栄養素として「たんぱく質」「ミネラル類」「ビタミン類」が挙げられます。「毎日そんなにたくさんの栄養素をとれない……」という場合はサプリメントなども活用し、健やかな髪を育てるための栄養をしっかり摂取するよう心がけましょう。
睡眠
- 髪の毛を作り出すための成長ホルモンは睡眠中に盛んに分泌されると考えられていることから、睡眠不足は育毛の大敵です。忙しいと睡眠時間が不足しがちになりますが、毎日の睡眠時間をしっかり確保できるようにしましょう。
成長ホルモンは入眠から3時間ほどでもっとも盛んに分泌されるといわれています。最低でも4時間の睡眠時間を確保すると良いでしょう。
また睡眠の長さだけでなく、質も重視しましょう。余計な光や音が入らない寝室環境を作る、寝る直前に食事をしないなど、睡眠の質を上げるよう工夫してみてください。
過度な飲酒や喫煙
- 毎日たくさんお酒を飲む習慣がある方や、たばこを吸う習慣がある方は薄毛の原因を作り出している可能性があるため注意が必要です。
お酒を飲むとアセトアルデヒドという体に有害な物質を取り込むのですが、肝臓で無害な物質に分解されます。しかし飲酒量が多いとアセトアルデヒドの分解が追いつかず、体内で悪影響を及ぼしてしまう可能性があるのです。また肝臓に負担がかかり、機能が低下することも、薄毛の原因となりかねません。
喫煙には血行不良を引き起こし、体内の老化を促進する、ビタミンCを大量に消費するなどの悪影響があります。
過度な飲酒もたばこもやめるのが理想的ですが、どちらも一気にやめようとすると挫折しやすく、ストレスの原因となる可能性が高くなります。無理をせずに、少しずつ量を減らすようにしてみましょう。
対策2.ヘアケアを見直す
薄毛を改善するためのヘアケアとして、毎日行うシャンプーとヘアドライの方法を紹介します。今日から実践してみてくださいね。
シャンプーの方法
- 1.乾いた状態で髪をとかし、もつれを取る。
2.たっぷりのお湯で湯洗いをする。
3.シャンプーを手に取り、水分を加えてよく泡立てる。
4.シャンプーを頭部全体になじませ、頭皮を揉むように洗う。
5.生え際や耳の裏などにも気をつけ、すすぎ残しのないようにすすぐ。
ヘアドライの方法
-
1.吸水性の良いタオルで押さえるようにタオルドライする。
2.ヘアオイルなどで髪を保護する場合は、地肌ではなく髪の毛につける。
3.頭皮を乾かすようにまんべんなく温風をあてる。ドライヤーは20センチほど離して使用するのがおすすめ。
対策3.ヘアスタイルを見直す

お気に入りのヘアスタイルは毎日したくなりますが、こまめに変えることで髪の毛や頭皮に与えるダメージを軽減することにつながります。薄毛対策だけではなく、イメージチェンジをしておしゃれを楽しむこともできますよ。ヘアスタイルを見直す際に取り入れたいポイントを紹介しますので、参考にしてみてください。
・ときどき分け目を変える
・髪をおろす日をつくる
・きつく結ばずにゆるく結ぶ
・ヘアアクセサリーを使用してバリエーションを増やす
・仕事で結ばなければならない場合、帰宅したら髪をほどいて休ませる
対策4.ストレスの発散方法を見つける
ストレスを感じないで生活することは難しいですが、発散方法を知っておけば、ストレスをため込まずにすみます。自然の多い場所を旅行する、趣味に打ち込む、カラオケで大きな声を出すなど、ストレス発散方法は人によってさまざまなため、自分に合った方法を探してみましょう。
対策5.育毛剤を使用する
育毛剤はドラッグストアなどで気軽に入手することができるため、毎日のケアに取り入れてみてはいかがでしょうか。血行を促進するものや潤いを与えるものなど、配合されている成分によって期待できるはたらきが異なるため、成分に注目して選びましょう。
対策6.頭皮マッサージを習慣づける
頭皮マッサージを取り入れると、頭皮の血行促進、ストレスの緩和、新陳代謝の活性化などの様々なメリットが期待できます。入浴時や寝る前などのリラックスタイムにぜひ取り入れてみましょう。
マッサージの際は髪の上から触るのではなく、髪の毛に指を差し入れて頭皮を直接揉むように動かしましょう。爪は立てず、指の腹を使うようにしてくださいね。
対策7.医療機関に相談する
セルフケアを続けても変化が見られない場合や抜け毛以外にも体調不良がある場合などは、医療機関を受診しましょう。薄毛の専門家である医師の検査や診察により、自分でも思いつかなかった原因にたどりつける可能性があります。注射や植毛など、医療機関でなければ受けられない治療もあるため、薄毛に悩んだら早めに専門のクリニックで相談してみましょう。
薄毛にまつわる噂 ウソorホント
薄毛の悩みはデリケートなため、なかなか人に相談できず、不意に目にした噂をうのみにしてしまいがちです。しかしその噂は本当なのでしょうか。この項目では薄毛にまつわる噂について解説しますので、噂に振り回されないための参考にしてくださいね。
噂1.ワカメを食べると髪の毛が増える
答えはウソです。ワカメ=育毛というイメージは根強いため、驚いた方も多いのではないでしょうか。ワカメが直接育毛に関わるわけではありませんが、ワカメに含まれる栄養素も、健やかな身体作りには大切です。髪の毛が生えるわけではないといってワカメを避けるのではなく、上手にメニューに取り入れてくださいね。
噂2.スタイリング剤が原因で薄毛になる
答えはウソです。ワックスなどを使うと髪の毛が細くなるという噂がありますが、実際は直接薄毛の原因になることはありません。
ただしスタイリング剤を長時間つけっぱなしにしたり、シャンプーできちんと洗い流さなかったりすると、頭皮が不潔な状態になって頭皮環境の悪化につながります。スタイリング剤をつけた日はシャンプーでしっかり洗い流しましょう。
噂3.豆乳は薄毛にいい
答えはホントです。これは豆乳に含まれる「大豆イソフラボン」に理由があります。大豆イソフラボンは植物性エストロゲンとも呼ばれており、女性ホルモンの一種であるエストロゲンと似たはたらきをします。男性ホルモンの量を抑え、抜け毛を減らすことに期待できるのです。目安として1日200mlほど、毎日飲むのがおすすめです。ただ、髪にはいいのは本当ですが、豆乳を毎日飲んだからと言って髪が生えるわけではありません。
噂4.帽子をかぶると薄毛の原因になる
答えはウソです。帽子で髪の毛を押さえつけることで薄毛の原因になると言われることがありますが、帽子をかぶることが直接薄毛に結びつくことはありません。薄毛が気になって外出に支障がある場合などは、帽子やウィッグの活用をおすすめめします。
ただし帽子をずっとかぶっていて頭皮が蒸れると、雑菌が繁殖しやすくなり頭皮環境の悪化につながる可能性があります。ときどき脱いで蒸れないようにするなどの工夫をしましょう。
噂5.筋トレをすると薄毛になりやすくなる
答えはウソです。筋トレをすることにより男性ホルモンが増加し、薄毛になりやすくなるという噂があります。しかし増える男性ホルモンは、薄毛の原因となる男性ホルモンとは別物であるため、薄毛とは関係ありません。
適度に体を動かして血行を促進すると薄毛対策になりますので、男性ホルモンが増えて薄毛が加速するかもと心配せず、運動するようにしてくださいね。
- Summaryまとめ
- 薄毛にはさまざまな原因があり、内臓疾患が関係しているケースもあります。薄毛改善のためのセルフケアはもちろん大切ですが、医療機関への相談も視野に入れましょう。医師に相談することで、ひとりで薄毛の悩みを抱え込むことによるストレスの軽減にも期待できますよ。
また記事内で紹介したように、薄毛に関する噂は信ぴょう性のないものも多くあります。噂に振り回されるのではなく、医師に相談したうえで行動を選択しましょう。
合わせて読みたい薄毛対策に関する記事
薄毛が始まっているかもしれないと不安に感じている方や、自分でできる薄毛対策を詳しく知りたいと思う方にはこちらの記事もおすすめです。自分に合った対策をとることで、早期の薄毛改善を目指しましょう。
- AGAスキンクリニックレディース TOP>
- 女性の薄毛研究室~FAGA Lab~>
- 「薄毛の予防法」記事一覧>
- 【医師監修】女性の薄毛対策。症状別の予防・対策法
今すぐ予約するならこちら
※宮崎院はお電話またはLINEにてご予約ください
女性の薄毛治療についての
よくある質問
-
薄毛・抜け毛の相談だけで予約しても大丈夫ですか?
-
女性の薄毛・抜け毛治療の費用はどのくらいかかりますか?
-
薄毛治療の費用を安く抑える方法はありますか?
-
女性の薄毛治療・FAGA治療では、保険は適用されますか?
ドクターからの回答
自由診療のため、保険は適用されません。女性型AGAも男性のAGA同様に、命に関わる病気でないとされているためです。ただし、お得にご利用いただける各種プランはご用意しております。
監修医師
AGAスキンクリニックレディース
診療顧問 田中洋平医師

- 【資格】
- 日本形成外科学会専門医
医学博士(信州大学)
- 【所属学会】
- 国際形成外科学会会員
日本美容外科学会会員
日本皮膚科学会会員
日本美容皮膚科学会会員
日本抗加齢学会会員
日本熱傷学会会員
日本救急医学会会員
日本フォトダーマトロジー学会理事
あわせて読みたい薄毛の予防法の記事一覧
-
薄毛の予防法

薄毛対策にはまず毎日の食生活の改善から
体を作っているものは、食べ物から摂取する栄養素です。納豆に七味唐辛子など普段食べる物に気を使っている健康意識の高い方でも、髪にいい…
2023/09/07
-
薄毛の予防法

【医師監修】栄養不足と抜け毛の関係性と摂取すべき食材
栄養不足と抜け毛の関係性と摂取すべき食材 外食やコンビニ食に頼った食生活では、さまざまな栄養が不足します。栄養不足は髪に悪影響を及…
2023/09/19
-
薄毛の予防法

髪型を工夫して、上手に薄毛をカバーしよう!
髪型を工夫して、上手に薄毛をカバーしよう! 薄毛で一番気になるのは、髪のボリュームと髪型でしょう。薄くなってペチャンとした髪は、見…
2023/09/19
-
薄毛の予防法

喫煙も薄毛の原因の1つです。喫煙による薄毛への影響についてご紹介します。
働き盛りの三十代、四十代にもなってくると、ストレス解消や集中力を保つために喫煙する人も増えてきます。そして、同時に段々と増えるのが…
2023/09/07
-
薄毛の予防法

女性の薄毛と食事の意外な関係とは?
女性の薄毛と食事の意外な関係とは? 女性にとって薄毛は大きな悩みのタネ。年々髪のボリュームが減ってしまうと、鏡をみるのも憂鬱になっ…
2023/09/21
-
薄毛の予防法

頭皮の日焼けが引き起こすトラブルと正しいケアの方法とは
頭皮の日焼けが引き起こすトラブルと正しいケアの方法とは 頭皮の日焼けを放置すると、赤みや痛み、乾燥などの症状が現れる恐れがあります…
2023/09/19
-
薄毛の予防法

春の新生活に薄毛対策
職場での異動、就職、引っ越し、短い期間に大きく環境が変わるのは春ならでは。春は環境の変化が激しいために、ストレスが溜まりやすい時期…
2023/09/07
-
薄毛の予防法

【医師監修】薄毛の予兆かもしれないサインとは
女性の薄毛はある日突然起こるものではなく、必ず予兆があります。その予兆を見逃さないために、薄毛のサインを知っておくことが重要です。…
2023/09/07
-
薄毛の予防法

【医師監修】プロテインと髪の毛・薄毛の関係とは?
プロテインと髪の毛・薄毛の関係とは? プロテインと言えば、筋肉を付けたい時に飲む栄養剤というイメージがある方が多いのではないでしょ…
2023/09/19
-
薄毛の予防法

脱毛症の予防・対策(ダイエット・食生活・ヘアケア)について
毛穴に汚れや皮脂が詰まることは、抜け毛の原因となります。出来るだけ毛穴や髪の毛は清潔に保つようにしておきましょう。シャンプーには…
2023/09/07
-
薄毛の予防法

【医師監修】薄毛予防・改善に役立つ食事とレシピ
薄毛予防・改善に役立つ食事とレシピ 薄毛予防や改善を目指す場合は、身体の内側から髪にアプローチすることが大切です。食事でタンパク質…
2023/09/19
-
薄毛の予防法

抜け毛の改善(食べ物・サプリメント)
髪の毛は細胞が分裂を繰り返すことで成長をしていきます。そのためには栄養を頭皮まで行き届かせる必要があり、そして栄養は血液によって運…
2023/10/19